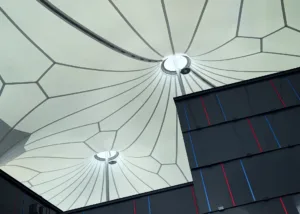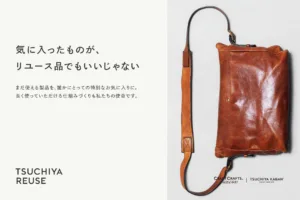モノが長く使われる社会の実現を目指すナガク株式会社が運営するウェブマガジン「NAGAKU MAGAZINE」では、その文化を体現するプロフェッショナルを紹介する連載『NAGAKU People』を始めました。リペアやリメイクを行う職人はもちろん、様々なプロジェクトに携わる方を紹介します。
今回お話を伺うのは、鎌倉・鵠沼を拠点に活動する、金継ぎアーティストの大脇京子さん。
金継ぎとは、欠けたり、割れたりした器を漆と金粉を使って新たな命を吹き込む、日本の伝統的な修復技術です。室町時代から続く技法で、茶道とともに発展してきました。割れた形自体を意匠として活かすのがその特徴で、近年は国内のみならず、海外からも注目されています。
そんな金継ぎに大脇さんが出逢ったきっかけをはじめ、金継ぎの技術や魅力、そしてモノを大切に使い続ける意義について教えていただきました。
大切にしていたマグカップが割れたことをきっかけに金継ぎ教室に

——まずはじめに、金継ぎに興味を持ったきっかけを教えていただけますか。
大脇さん:もともとはファッション関係の仕事をしていて、大量生産・大量消費が当たり前の環境にいました。意識を変えるきっかけとなったのは、結婚し、子どもが生まれたことです。
まず最初に興味を持ったのは、食。子どもの口に入るものを気にかけるようになったら、その生産環境やフードロス問題をはじめ、その先にある環境問題についても考えるようになって。なかでも、食事を盛り付ける器は身近だったこともあり、“とりあえず買ったもの”ではなく、心から気に入ったものを長く使いたいと思うようになりました。
ですが、形や装飾に手が込んだ器や、陶芸作家による一点ものの器などは、それなりのお値段がしますよね。お気に入りのものを使いたいと思う反面、割ってしまうのが怖いという思いもありました。
——その当時は、金継ぎについてはご存じだったのでしょうか?
大脇さん:言葉は知っていたものの、実際に見たことはなくて。でも、ちょうどその頃、たまたま見ていたテレビで、金継ぎされた器を見る機会があったんです。黒田雪子さんという方の作品だったのですが、本当に美しくて衝撃を受けました。今でも、テレビ画面に器が大きく映された、あのときの映像を鮮明に覚えています。

——その作品を見たのが、金継ぎを始める大きなきっかけとなったんですね。
大脇さん:はい。ですが、直接的なきっかけとなったのは、大切にしていた「アスティエ・ド・ヴィラット」のマグカップを、子どもが割ってしまったことですね。ショックでしたが、お気に入りのマグカップだったので、捨てるという選択肢はありませんでした。
「金継ぎで直そう!」と思い立って、すぐに金継ぎ教室に通うことを決めました。当時は熊本県に住んでいたのですが、福岡県の金継ぎ教室に月2〜3回ほど通い始めました。
その後、先ほどのマグカップは1年ほどかけて、なんとか直すことができました。複雑に割れていたので、破片を接着して整えるのに時間がかかってしまって…。地味な作業でしたが、その修復の過程で金継ぎの基礎や面白さを教えてもらって、今の私がありますね。
使う人の日常に溶け込むような器に仕上げるのが理想

——先ほど、破片の接着に時間がかかったというお話が出てきましたが、金継ぎの工程の全体像はどのようなものなのでしょうか。
大脇さん:まず漆で割れた部分を接着し、接着剤が乾いたら研磨して表面を滑らかにします。さらに何度も漆を塗り重ねて継ぎ目をきれいにし、最後に金粉で継ぎ目を装飾します。漆は気温や湿度の変化によって固まる速度が変わるため、器によっては数ヶ月かかることもあります。
中でも、漆を塗り重ねる下地作りは大切な工程です。これは、福岡県で通った金継ぎ教室での教えが生きています。
器は磁器や陶器、ガラスなど素材がたくさんありますし、割れ方もさまざま。漆の染み込み具合も器によって違うので、一つ一つにしっかり向き合わないといけないんです。大変ですが、ここで妥協してしまうと、それは仕上げのときに絶対に現れます。だからこそ、下地作りは特に丁寧にやっていますね。

——金継ぎをする際に心がけていることはありますか?
大脇さん:器をより良く、美しくすることでしょうか。日常使いに耐えられるように直すのはもちろん、器をより美しく見せるために、ものによって仕上げを変えています。たとえば、白い洋食器や青い絵付けの器には、金粉ではなく銀粉を使って、継ぎ目が目立ちすぎないようにすることも。金粉や銀粉がマッチしないと思ったら、赤茶色の漆を使って仕上げることもありますね。
あとは、依頼者から普段の使い方を聞いて、仕上げのやり方を考えることも多いですね。金継ぎはアートの側面も強いですが、使う人の日常に溶け込むような器に仕上げるのが理想です。
人それぞれ大事なものは違うからこそ、どんな器でも気兼ねなく依頼してほしい

——さまざまな器の金継ぎをされていると思いますが、特に印象的だった依頼はありますか?
大脇さん:どれも思い出深いのですが……息子さんが初任給で買ってくれた器や、新婚旅行で買った器を持ってきてくださった方はよく覚えていますね。
金継ぎというと、高価な器や骨董品にするものというイメージがあるかもしれませんが、そんなことはなくて。決して高価なものでなくても、その人にとって思い出が詰まった器であれば、それはまぎれもなく大事なもの。人それぞれ大事なものは違うからこそ、どんな器でも気兼ねなく依頼してほしいと思っています。
——金継ぎをしていて、どんなときにやりがいや嬉しさを感じますか?
大脇さん:やっぱり、金継ぎした器を手渡したときに「ありがとう」と喜んでくれる瞬間ですね。
お母様やお祖母様の嫁入り道具を依頼されたことがあるのですが、それを直して渡したときのうれしそうな顔が忘れられません。その器は、これから子どもや孫の世代に繋がって使われていくはず。それってすごく素敵なことですよね。金継ぎを通して、そのお手伝いをできることがうれしいです。
お気に入りのものをたくさん使ってほしいから

——金継ぎを日常生活に取り入れることで、どのような変化が生まれると思いますか?
大脇さん:器の金継ぎをしてから、食卓に取り入れる頻度が多くなったとか、子どもにも使わせるようになったというお客さんは多いですね。割れてしまっても金継ぎで直せるから、使うのが怖くなくなったと。
お気に入りの器は、大事だからこそ奥にしまい込んでいる人も多いはず。でも、それはもったいないと思います。そうならないためにも、お気に入りのものはどんどん使ってほしいんです。好きなものに囲まれて暮らすって、とても豊かなことですから。