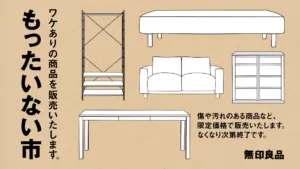モノが長く使われる社会の実現を目指すナガク株式会社が運営するウェブマガジン「NAGAKU MAGAZINE」では、その文化を体現するプロフェッショナルを紹介する連載『NAGAKU People』を始めました。リペアやリメイクを行う職人はもちろん、様々なプロジェクトに携わる方を紹介します。
今回ご紹介するのは、大阪で活動する横振り刺繍作家の尾崎ふみなさんです。横振り刺繍とは、針が左右に動くミシンを使い、職人が直接生地に絵や文字をデザインする技法で、コンピュータ式ミシンとは違い、刺繍に厚みと立体感が出るのが特徴。もともとは打掛や振袖などの和装品に多く用いられてきましたが、戦後はスカジャン(横須賀ジャンパー)への刺繍で一躍有名になりました。
そんな横振り刺繍に魅せられ、現在、作家としてオリジナル作品の制作などに取り組む尾崎さん。横振り刺繍に出会ったきっかけから、その魅力、現在の活動などについてお話を伺いました。
横振り刺繍に魅せられ、独学で技術を習得
——まずはじめに、横振り刺繍に興味を持ったきっかけを教えてください。
尾崎さん:高校生の頃から古着やアンティークのものが好きで、その延長で着物にも魅力を感じるようになりました。着物の専門学校では和裁を中心に、着付けや染色、デザイン、ヘアメイクスタイリングなど着物全般について学び、専門学校卒業後はリユース着物やアンティーク着物を扱う着物店に就職したんです。そこで出会った戦前に作られた刺繍帯が、特に印象に残っていました。
その後、2017年頃にたまたま横振り刺繍の製作中の動画を見る機会があったんです。そのとき、「糸で絵を描いてる!」と感動して、すぐに「やってみたい!」と思いました。それから横振り刺繍ができるミシンを探し始めました。

とはいえ、横振り刺繍ができるミシンは針が左右に動く特殊なミシンなので、何を買えばいいのかネットで調べながら2〜3ヶ月ほど迷っていて…。そんな中、たまたま家の近くにアンティークのミシンを売っているお店を見つけて、「これは運命だ」とすぐに買いに行きました。
——ミシンを買われてから、どのように技術を身につけていったのでしょうか?
尾崎さん:独学ですね。そもそも横振り刺繍をやっている人が少ないので、どこかで習えるわけではないんです。職人さんに弟子入りして教わることはできると思いますが、職人さんがいるのは横振り刺繍の産地として有名な群馬県桐生市や、スカジャンで有名な神奈川県横須賀市など。私の住む大阪からは遠くて、独学でやるしかなかったんです。
当時は、ネットにも横振り刺繍に関する情報が少なくて、完全に手探りでやっていました。最初の3〜4年くらいは失敗の連続で、試行錯誤しながらちょっとずつコツをつかんでいった感じです。ただ、そのときはまだ着物店で働いていたので、横振り刺繍は休日にやる趣味の一つ。「楽しい!」という気持ちだけでやってましたね。

その後、ある程度技術が身についてきた2020年頃から個人の刺繍作家として活動を始めました。2022年頃には横須賀美術館の開館15周年記念企画展「PRIDE OF YOKOSUKA スカジャン展」に横2メートル、縦1.5メートルの大きな作品を出展し、いい経験になりました。ちょうどその頃からオーダーも増え始めて、「依頼をかたちにする」を繰り返していくうちに今の自分の作風が確立されていったのかなと思います。
個人の刺繍依頼のほか、立体刺繍も手掛ける

——あらためて、横振り刺繍のやり方や特徴を教えていただけますか?
尾崎さん:刺繍する絵や文字などを紙に書いて、それを布にトレースし、その線に沿って刺繍をしていきます。スカジャンによく使われる虎の刺繍など、伝統的なデザインはフリーハンドでやる場合もあります。
特別な工程や決まりはないため、「横振り刺繍はセンス」ともよく言われます。絵を描くのに近いので、刺繍の技術というよりは美術的な技術やセンスの方が重要かもしれません。
もう一つ、横振り刺繍で特徴的なのは、「横振りミシン」という専用のミシンを使うことですね。通常のミシンは針が上下に動きますが、横振りミシンは針が左右に動きます。どれだけ左右に振るかは、右足の膝部分にあるレバーを動かして調節します。通常のミシンと同じように手の動きと足のペダルがあって、それにプラスして膝の動きがあるので、はじめは扱い方が難しいです。あとは、急に針を動かすと糸が切れてしまうので、そのミシンの特徴をつかむことも必要ですね。

——これまでに手がけた作品のなかで、印象に残っているものはありますか?
尾崎さん:「お父さんのプレゼントに」と依頼していただいた、前掛けの刺繍が特に印象に残っています。誕生日が春で、釣りが好きとのことだったので、桜と魚をモチーフにした刺繍を施しました。お客様のお父様に対する深い愛情が伝わってきて、私も期待に応えられる作品にしようと思い取り組みましたね。その方は、翌年にもお父様へのプレゼント用にと依頼してくださって、リピートしてくれたのもうれしかったです。
——刺繍をする際に、意識していることはありますか?
尾崎さん:依頼されて刺繍をする場合は、お客さんとしっかりとコミュニケーションを取ることを大切にしています。「こういう刺繍をしてほしい」と内容がしっかり決まっている場合は、お客さんのイメージとズレがないように何度もすり合わせをしますし、ふわっとしたイメージで依頼される場合は、いくつもラフを提案して、一緒に具体的なイメージに落とし込むようにしています。
——個人からの依頼のほかに、企業とコラボレーションもされていらっしゃいますが、特に印象に残っている事例はありますか?
尾崎さん:「グラキリス」という塊根植物をモチーフにした、立体的なオブジェを刺繍で作ったのが印象に残っていますね。立体物を作るのは初めてだったので、自分の中でも挑戦的な作品になりました。
はじめは粘土で形をつくってイメージを固めて、他のアーティストさんとも相談しながら進めていきました。ぬいぐるみを作るのと同じように、刺繍した生地を縫い合わせ、中に綿を入れているのですが、刺繍に厚みがあるので意外とずっしりしています。今後はこういった立体物にも挑戦していきたいと思っています。
長く使えば、愛着が湧いてモノに魂が宿る

——今後は、どのような挑戦をしていきたいと考えていらっしゃいますか?
尾崎さん:先ほどお話したような立体刺繍や、大きな作品作りにもチャレンジしていきたいです。あとは、お客さんのオーダーをその場で刺繍するといったような、実演もやってみたいですね。
——活動の幅を広げていくなかで、刺繍作家として大切にしていることはありますか?
尾崎さん:自分の中で100点のものを作ること、ですね。そのためにも、作っている途中で「なんか違うな」と思ったら、その違和感をほったらかしにせず、作り直せるものはもう一度作り直すようにしています。
なんとなくの違和感でも、作業を進めていくとその違和感が大きくなって、最終的に納得のいかないものになってしまうんです。どんな作品であっても、自分の中で完璧だと思えるものを目指しています。
——尾崎さんが思う、横振り刺繍の魅力はどんなところでしょうか?
尾崎さん:人の手で作るからこその暖かみがあるところですかね。横振り刺繍って、同じところに何度も糸を重ねていくので、ボコボコして厚みが出るんです。そのため、光の当たり方で刺繍の印象が変わり、見る角度によってもさまざまな表情があります。一方、コンピュータ刺繍は厚みがなくてフラットなのが特徴。個人の好みではありますが、コンピュータ刺繍にはないボコボコ感や陰影のある感じが好きですね。


——最後に、「モノを長く使う」ことについて、尾崎さんの考えを教えていただけますか?
尾崎さん:愛着が湧いて、モノに魂が宿るようなことなのかなと思います。
私の身近なものを例に挙げると、仕事道具のミシンが100年近く前から使われているもので。「私の前にはどんな人が使っていたんだろう」と想像するのも楽しくて、いろんなストーリーがこのミシンには詰まっていると思うんです。あとは、ミシンにも癖とか個性があって、長く使っているとそれが顕著になってくるんですが、それも含めて愛おしいなと思いますね。
とはいえ、こんなふうに長く使うためにはメンテナンスが必要不可欠。日々手入れをしていますが、それでも「今日は動きが悪いな」という日もあって、そういう日は無理しないようにしています。ミシンの調子を見ながら付き合っていく、それがモノを長く使うための秘訣なのかなと。私もそんなふうに愛してもらえる作品を作っていけたらと思います。